
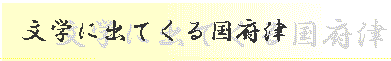
| 佐多 稲子 「くれない」 |
|
昭和27年 新潮社 |
「夏行った国府津、覚えてるかい。」 「僕、よく知ってらあ。海があるんだろ。」 「よしよし。」 岸子が笑ってる間に明子は長男の靴を脱がせてやった。汽車はもう動き始めていた。 (中略) 明子はこの夏のことを思い出さずにいられない。国府津には岸子の実家の別荘がある。子供に海を見せたいという明子の母親らしい希みを聞いて岸子はるす番がいるだけのその海岸の別荘を思い出し、自分が先に行っていて、明子たちを呼んだのであった。その時は明子の夫の柿村広介も一緒であった。長女の徹子も連れていた。広介と明子にとっては、子供を連れて汽車に乗るということも始めてであり、広介がプロレタリアの文学活動をしたために起訴されて、二年近く妻子と別れて不自由な生活をし、帰って来てから始めての旅でもあった。窓から顔をさし出す子供たちの背をそれぞれ押えながら、時々目を見合わせて、そっと、愛情深く微笑んだりした。 今日岸子と二人きりの話の末に、ふと思い立って、今またその国府津への汽車にのっている。 |