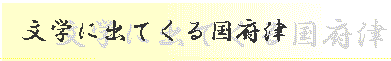|
間もなく、ガラガラと凄じい音響の底へ引き入れられると、欄から白い烟(けむり)が濛々と舞い込んで、黄色い鈍い燈(ともしび)の光が、蒸し暑い部屋の中に濁り漂った。汽車は暫らく八つのトンネルを出つ入りつした。「此のトンネルさへ越して了へば、国府津は直だ。」と彼は思った。覚えのある派手な琥珀の日傘をさしてプラットホームに彳んで居る美代子の俤(おもかげ)が、彼にはもう見えるやうな気持ちがした。小山を過ぎてから、野と海とが再び近づき始めた。恋人の生まれ故郷の相模の国、なつかしい相模の国の、はるばると続いた平原の果には、水蒸気の濃い靄が、金色の光に燃えて打ち煙って居た。ところどころに波うつ丘陵の青葉の匂や、大空の雲の勢や、紫がかった遠山の風情まで、悉く親しみ深い相模野の景色であった。酒匂川の鉄橋を渡る時、足の下にはそも涼しさうな水が笑って
、橋杭のぐるりに渦を巻きながら流れて行った。其の水の注ぎ落ちる川下の浜の方には、ざぶんざぶんと相模灘の怒濤の崩れる音が聞えて、飛沫(しぶき)の末が灰のやうに舞い上った。汽車は次第に速度を弛めて、途かに停車場の構内に馳せ入った。「国府津。…国府津。」二三人の駅夫がこつこつと靴を鳴らして通った後から、乗り降りの客が忙しげにプラットホームへ下駄を引き擦って歩いて居た。箱根帰りのが一隊らしい五六人の男女の群が、どやどやと景気よく二等室へ跳び込むや否や、大声で暑い暑いとこぼしながら、傍若無人に扇を使ったり、ハンケチを振ったり冗談を云い合ったり、忽ち車内は賑やかになった。
|