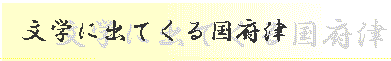|
母と兄夫妻とは、其の日の午後に熱海を出帆する船に乗つて、国府津の沖合いへ着いたのはもう日がとつぷりと暮れてからであつた。それまで生きた空もなく突つ伏して居た母は、やつと少し元気を出したが、艀へ乗り移るのが又一と苦労であつた。彼女は恐らく、つい二、三丁鼻の先に国府津の町の灯がチラチラ見えて居なかつたら、それに乗り込む勇気はなかつたであろう。母自身に云わせたら「全く死ぬ気」で乗り込んだであろう。彼処、の海は可なりたちの悪い処で、おまけに其の日は夕方から風が出たりして、波が高かつたのである。のみならず小さな船には乗り切れないほど一杯客が乗つて居た。
|